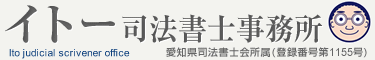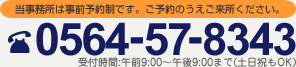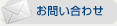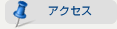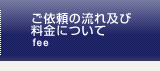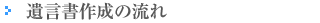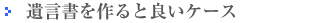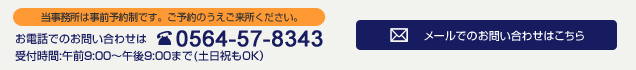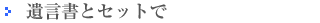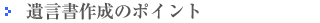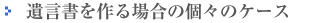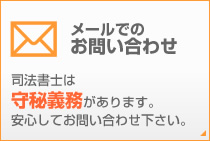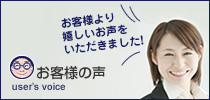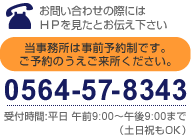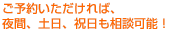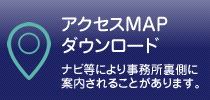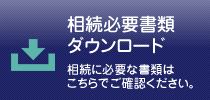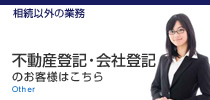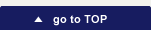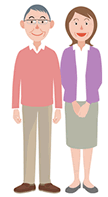
遺言書とは、亡くなった後にあなたの希望を実現するために作る法的なメッセージです。
遺言書を作ると、あなたの死後ご家族が遺産分配の話し合いをせずに、あなたの財産をご家族にそれぞれ譲り渡すことなどができます。
遺言書には大きく分けて次の2つの種類があります。
- ・自筆の遺言書:
- 書いた後の保管とあなたの死後に裁判所の手続が必要となりますが、お手軽でなるべく費用をかけずに作ることができます。
- ・公証役場で作る遺言書:
- 公証役場の費用がかかりますが、遺言書が公証役場でも保管され、あなたの死後裁判所の手続きなしで使うことができます。
イトー司法書士事務所は、あなたが亡くなった時に備えることはもちろん、
あなたの想いを大切な人たちに伝える遺言書をご提案します。
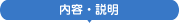 |
 |
|
|---|---|---|
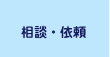 |
|
|
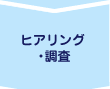 |
|
|
 |
もしもの備え&想いを大切な人たちに伝える提案

|
|
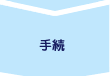 |
|
(公証役場へ行く場合)
|
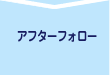 |
|
|
- 任意後見契約書
-
あなたが認知症になってしまった時に備えて、
財産管理人(任意後見人)と財産管理内容をあらかじめ公正証書で作っておく契約書です。
任意後見契約書を作ってない場合、あなたの家族などの申立てで裁判所に財産管理人(成年後見人)を選んでもらうことになります。
この場合、誰が成年後見人になるかをあなたが決めることはできません。
また、財産管理の内容も、原則あなたの財産をなるべく減らさないようにすることに限定されてしまいます。
もしもの時にあなたの希望を財産管理人や財産管理内容に反映したい場合は、任意後見契約書を作っておきましょう。 - 尊厳死宣言書
- あなたが脳死状態になった時に延命治療を望まない場合、あらかじめその意思を書面にしたものです。あなたの希望をかなえるとともに、ご家族が判断に迷わなくなります。
- エンディングノート
-
遺言書を作る前に、または遺言書を作ると同時に、エンディングノートも作ってみませんか?
>>エンディングノートについて詳しい内容はこちら。
- ・早く作りましょう
-
遺言書は、認知症になってしまうと作ることができません。
15歳以上の方なら遺言書を作ることができるため、思い立ったらすぐ作りましょう。 - ・家族内のコミュニケーション
-
あなたが遺言書で希望していることと、ご家族の想いが違っていることはよくあります。ご家族に納得してもらった上であなたの希望を実現するためにも、あなたが遺言書を作った想いやご家族への感謝の気持ちなどを遺言書や別の手紙で書き残してみましょう。
普段からご家族とコミュニケーションを重ねておくことが一番です。 - ・作った後のフォロー
-
遺言書は作ってから実行するまでに時間差があり、その間にヒト・モノ・カネの変化があります。
そのため、あらゆるケースに完全に対応した遺言書を作ることは非常に困難です。
従って、あなたの誕生日などに定期的に遺言書を見直したり、場合によっては新しく作り直しましょう。
また、自筆の遺言書は、なくさないように保管にも気を配りましょう。
結婚した時や子供ができた時など、あなたに大切な人ができた時に作りましょう。また、勤め先を退職して第2の人生を踏み出す時など、あなたの人生の節目に作ってみましょう。
- 子供がいないご夫婦
-
遺言書があれば、あなたのパートナー(ご主人や奥様)は、あなたの親や兄弟と遺産分配の話し合いをしなくても済みます。また、あなたの兄弟には遺留分(※)の権利がないため、親もいない場合は遺言書であなたの財産のすべてをパートナーに残すことができます。
※遺留分=相続人の最低限の取り分 - 行方不明や認知症の家族がいる
-
遺産分配の話し合いは相続の権利をもつ家族全員としなければなりません。もしあなたの家族の中に行方不明や認知症の方がいると、話し合いの前提としてまず裁判所の手続が必要となり、その分時間と費用がかかってしまいます。
遺言書があれば、この裁判所の手続きなしで遺産分配ができます。 - 離婚経験のある方、または再婚した方
-
離婚相手があなたの子供を引き取っている場合、その子供にも相続の権利があります。また、その後再婚相手との間に子供ができた場合、再婚相手とその子供は離婚相手側の子供を交えて遺産分配の話し合いをしなければなりません。
遺言書があればお互い顔を合わせずに遺産分配ができます。 - 籍を入れていない同棲相手がいる
- 籍を入れていない同棲相手、いわゆる事実婚・内縁夫婦の方には相続権がありません。遺言書で同棲相手に自宅などを残すことができます。
- 子供のパートナーや孫にも遺産を渡したい
- 子供のパートナー(夫や妻)や孫には、どんなにお世話になっていても相続権はありません。遺言書で養子縁組をせずにあなたの財産の一部を渡すことができます。
- 独身で身寄りのない方
- 独身で身寄りが全くない方の財産は最終的には国のものになってしまいます。遺言書であなたの財産を友人に渡したり、慈善団体へ寄付することができます。
- ペットを飼っている
- あなたが可愛がっているペットに財産を譲ることは、日本の法律ではできません。遺言書で信頼できる人に財産を譲るかわりに、ペットを大切に世話してもらうお願いができます。
- 事業をやっている
- 個人事業主や会社経営者などは、事業のすみやかな継続のために、遺言書で事業用不動産や自社株などを後継者に集中して引継がせることができます。